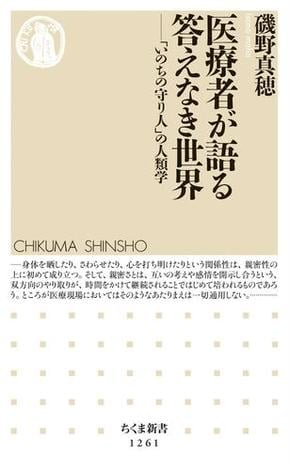- Amazon.co.jp ・本 (312ページ)
- / ISBN・EAN: 9784393333365
作品紹介・あらすじ
思春期の女性はなぜ痩せたがるのか。医療の視点では捉えきれない摂食障害の内実をエスノグラグラフィーの手法(「語り」)を援用しつつ、現代における食の本質を解明する試み。
感想・レビュー・書評
-
「私たちはこうしたら未来が保証されるとか、これに依拠すれば世界に安寧というような社会全体の現在と未来を保証する『大きな物語』を失った時代に生きている。」本文P.85
本著は、6名の摂食障害の女性たちから聞き取ったそれぞれの事情や背景をとても具体的に説明している。加えて明確なデータや引用元・参考文献を示した著者の考察がとても信頼できる印象を受けた。
どの女性たちも始めは大掛かりなダイエットを目指していたわけではない。
ひょんなことがきっかけで、気づくと摂食の問題から抜けられなくなり、そういう行為でしか達成感や満足感を得られなくなっているという状況に、こちらまで苦しさを覚えてしまった。
過去に、摂食障害は家庭内の問題、殊に母娘間の葛藤等に起因するという流れもあったが、本著により原因は必ずしもその一点ではないことがよく分かった。
体質的な食欲調節機構や遺伝的脆弱性など【生物学的要因】、性格・思考・発達障害・精神疾患併存等の【心理発達要因】、家庭や社会文化環境などの【社会・環境的要因】等が、複雑に絡み合い発症するとのことだ。
昨今、「母親」や「家族」「母性」に絶対的価値を置く一義的な「神話」が否定され始め、著作、文学作品、そしてSNS界隈でも「毒親」「アダルトチルドレンAC」のワードが氾濫するようになった。
母親や家族から受けた心の痛み等を気づいて、できる時に安心して言語として表出し、「毒親」「アダルトチルドレン」という言葉の轍にはまり込まないことを目指したい。
「あんなこと、こんなことは、私の所為ではない」と自分を解き放ち、被害者の役割から外れて、自分の人生を進んでいくことが大事かなと感じた。
失敗が許されず、テレビ等で事の大小にかかわらず謝罪会見が繰り返される。
他人と少しでも異なる意見には炎上で相手を攻撃する。私たちは常日頃、誰かに攻撃される不安に苛まれ、正しさや他人への思いやりばかりを求められる窮屈な環境に窒息しそうになっている。
こんなに豊かな時代なのに不安でいっぱい。だから確固たるものが欲しい。誰かに受け入れられたいと、他人からの評価に右往左往し、体重や「いいね」やフォロワー数などの数値化された尺度にすがるような気がする。
「食べ物と人生の意味が硬直化し、流動性を失っていることがわかる。食べ物や人生に自ら意味を見出すことをやめ、他人の作った意味にただ従属していることがわかる。」P.724
「私たちは、生きるために、食べる。
それはとても当たり前のことのように思える。
しかし『生きる』とはどういうことだろう。どうやったらきちんと『生きている』と言えるのだろう。どう死んだらきちんと『生きた』といえるのだろうか」P.11詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
多面的に「普通に食べられない」ことに関して考えている。
病気という「免罪符」が必要な人がそのために摂食障害になっているという側面。
なんというか、なんというか、、
全面的に「寄り添う」必要はあるが根本解決にはその「承認欲求」「かわいそうだと思われたい」心を無くさないといけない。同情だけでなく冷静な目でその真因を探るというアプローチも必要だと感じた。
真因はいろいろあるとして、摂食障害の人と関わる際に私たちには何ができるのだろうか。わからなくなってきた。 -
私たちの世代が「摂食障害」と聞いてまず思い出すのは、Yesterday once moreなどの名曲で知られる「カーペンターズ」のカレン・カーペンター。当時私はわざわざ写真週刊誌「フォーカス」を買い、カレンの写真を見て慄然としたものだ。そこに写っていたのは、力石徹を実写化したかのように顔の肉が落ちて病的に見えたカレンだったからだ。
こんな印象があるので、摂食障害を「病的」と結びつける私の連想は、世間一般から見てもあながち的外れとは言えないだろう。ところが磯野さんはそこに疑問を持った。
-摂食障害の研究が進み多くの論文が書かれたにもかかわらず、現状は摂食障害に効果的な治療法が確立されたとはとても思えないではないか?
-と言うことは、摂食障害を病気として治療を施すというアプローチ自体が根本的な発想の誤りなのでは?
そこで磯野さんは、摂食障害を「ふつうに食べられない状態」と言い換えるところからスタートしている。そして磯野さんは、病気の治療または障害の除去という従来の概念からできるだけ離れようとするために、本書では6人の当事者女性へのインタビューを試みている。それは医療者が患者に対するようなものではない。またジャーナリストによる聞き込みのようなものでもない。まるで姉が妹の話を聞くかのよう。
でもインタビューの録音起こしを読んだ当初は、当事者の行動は正直に言って理解できなかった。病気以外の何物でもないとさえ思った。しかし磯野さんは違った。まるで小さい子どもがいくら駄々をこねようとも根気よく付き合い、結果的に子どもの言動すべてを受け入れて成長を促す母親と同じようにして、既存の摂食障害の研究分野では接点がなかったさまざまな分野からの引用を当てはめ、摂食障害の本当の姿を見極めようとしている。この本が読みやすいのは、磯野さんのそのような“優しい視点”があふれているからなのだろう。
磯野さんが本書で引用した知見で、私の目が留まったものをあげておく。
まず1つ目が、なぜ当事者があえて、きつくて不快な拒食過食に自分自身から入り込むのかを考えるのに、心理学者ミハイ・チクセントミハイの「フロー」という概念を引用していること。
『(チクセントミハイは)チェスやロッククライミングなど、多くの技能や努力を必要としながらも金銭や名誉といった外的報酬がほとんど得られず、時には命さえも危険にさらすような行為に、なぜ人は夢中になり、それに楽しさを感じるのかという問いを立て、それをフローという独自概念のもとに説明した…
…自己目的的経験は、それ以外の生活が往々にして退屈であるのとは異なり、退屈ではない。同時に「通常」の生活の中では意識の中にしばしば入り込んでくる不安を生み出すことがない。退屈と心配とが相殺し合っていることから、自己目的的経験は行為者をその活動に完全に没入させてしまうものの一つとなる。その活動は絶えず挑戦を提供する。』
そしてもう1つ。心理学者のスーザン・アルバースによって提唱された、マインドフルな食べ方(Eating Mindfully)という概念の紹介。それはつまり「『自分の行動、考え、感情』のすべてに真摯に注意を払い、よく理解する」というマインドフルな食を通じて、身体と心が送る合図に注意深く耳を傾け、敏感に応えることで、失われた食に対するコントロールの感覚を取り戻し、健康的な食事を取れるようになるというものだ。
しかし磯野さんはその着眼点には否定的だ。まるで“ながら食べ”や会食は避けるべきで、食に意識を集中させる食べ方が第一であるかのような考え方に対し磯野さんは、いやいや、実際にはマインドレスな食べ方をしている人でも、多くの人はふつうに食べられなくはならないでしょ、と疑問を呈している。
以上のとおり本書の一部を拾ってみただけで、今まさに生活している当事者がどう日常を過ごし、その結果どう食べているかという、現実のありのままの姿に磯野さんは焦点を絞っている。そして当事者がピンとこないものは、主流の学説であってもあえて距離を置こうとしているのがわかる。
その結果私が得た見解は、拒食や過食は病気と言うよりも、むしろ嗜癖や、人間誰もが陥る快楽の追求であり、それ以上でもそれ以下でもないということ。つまり、二日酔いに悩まされながらも飲酒がやめられない状態や、ランナーズハイの仲間なのだ。だから、摂食障害を治療することがその人にとって回復の獲得につながるとは限らないのだ。むしろ摂食障害と共存することで、その人らしく安定して(安定という言葉が矛盾と感じるかもしれないが)生活できるのだ。
その点の記述だけでも、この本は当事者やその周囲の人を大きく安心させる力を持っている。
一方で、私の疑問である「なぜ摂食障害は女性が圧倒的に多いのか」や「世界的に見れば、なぜ欧米や日本で多く発生しているのか」の答えは出ていない。なので、拒食過食の状態から解き放たれたいと考えたとき、本書からノウハウを見いだせる機会は少ないと思う。
そのことは、冒頭のカレンが32歳の若さで死に至ったのをどうしたら止められたのかのヒントを本書から見いだし難いことが裏付けている。死亡当時は色々な憶測も書かれていたが、結局は当人でないとわかり得ない。いや、当人ですら解明できないかもしれない。
しかしながら、私はあえてこの本が多くの悩める人を安心させる可能性を有していることをもって、この本を☆5で評価したい。 -
「私たちは生きるために食べていると言えるのだろうか。私たちは科学的に正しい食べ方をし、専門家の目から見て適切な心身を作るために生きているのだろうか。」
摂食障害の患者6人にに、4年間聞き取りを行い、「なぜ普通に食べられないのか」を問うた本。構成としては、まず1章で聞き取りを上げ、「ふつうに食べられない人生」を並べる。2章で現在の医学的視座から、摂食障害のなおしかたを描き、そしてそのなおしかたと向き合った6人の体験を並べている。現在の病の理解では著者曰く「還元主義」という考えに基づいて、その還元主義に基づいた治療方針が立てられているという。
「摂食障害に関する代表的な議論を分野問わず通読すると、原因や症状の維持に関与するとされる要因は、時代や学問領域によって変化を見せるものの、原因や症状の維持のメカニズムは、全て同一のフレームワークによって理解されていることがわかる。このフレームワークを「本質論」と「生体物質論」よりなる「還元主義」と名付け」ている
「本質論」は心の問題から摂食障害が起きているという考えで、「生体物質論」は摂食障害は身体の問題で、身体は物理、化学的に分析できるとしている論である。
つまり、我々の身体は、そして我々の身体を維持するための食事というものは、こころとからだから構成されている、そしてどちらかに問題があるからその問題を治そうということである。
そしてその心と体をめぐる治療法や考えが並び、それに対する著者の考えが描かれてゆく。
「痩せたい」と人はなぜ思うのか?わたしは痩せたいと思うし、痩せたいがために糖質制限や運動、カロリー計算や食事の記録を行なっている。その動機となるのは「痩せている方が良いと思う」からだ。痩せている方が美しいとされる、男性が結婚相手に臨む指標は容姿がダントツだそうだ、また、痩せている方が自己管理ができ、賢いとされる、体に良いものを選択し、適切な自己管理ができているとされる。そして、食事の制限や痩せは、やればやるほど成果が出るため、ある程度の達成感や承認を得ることができるのだ。6人の語りの中にも、それは数多く見られる。
さて、食事とはなんなのか?「ふつうに食べる」とはなんなのだろうか?著者はふつうにたべることは食は複雑であり、さまざまな前提や背景を共有することで行われる社会的な連帯であるとする。生まれながらにして獲得する本能では無い。たとえば食べる時間、食べる道具、何を食べればいいのか、食のマナー、調理法、栄養、それらは文化的なものだ。はしの持ち方がなってないだとか、行儀悪いだとか、食べ合わせだとか言うことも、学んでいく知識だ、それらの知識があって初めて、人とふつうに楽しく食べることができる。食は文化である。そして、その食をコントロールすることで得た身体の社会的な評価もまた文化である。痩せていることが美しいとされる文化、身体をコントロールすることが賢いとされる文化、そして食をふつうに楽しむこともまた文化である。しかし摂食障害とは病であり、この病に対し、医学が治療を行う。治療は科学的なものだ。科学的なものさしと、文化的なものさしの狭間にこぼれおちた「ふつうに食べること」ついて丁寧に語られている。
この本はとても優しい眼差しで書かれていて、そして同時に「痩せたい」と思ったことのある人間に対してはある意味猛毒であるような気がする。なぜなら、「痩せることが美しい」社会は全く変わらないからだ。痩せたいのであれば、ここに描かれた体験をそのまま実行しさえすればいい。彼女たちの語りは、とても魅惑的だ。悩んではいるが、確かにそれにより痩せた体を獲得しているのだ、それが例え一時であり、それがたとえ生きていく上で地獄のような悩みとしてあらわれたとしても、確実に痩せる術が並んでいる。そして同時に、それを読む人がどう捉えるかと言う問いかけにもなる。ふつうにたべることは難しい、自己コントロールは賢い、ふつうに食べることの喜び…。この本にどんな感想を抱くかは、生きていくことと食事に対する自分の考えを浮き上がらせることになる。
食事は、人間の暮らしと人間の形を作るものなのに様々な事が勝手に専門家やら他人にとやかく言われることだ。糖質制限もカロリーも、あれがおいしい、あれが健康にいい、バランスの良い食事だとか、そんなこと全部やめてしまった方が早いのではないだろうか?
「食べ物と他者はよく似ている。なぜならそれらはふたつとも、人間にとって怖いからである」
あとがきに書かれた最初の一文。
食べることとはなんだろうか、どうして痩せていることは病なのか。
「痩せたい」と一度でも思ったことのあるすべての人が、この本を読むことを願う。 -
食べることを当たり前にできていることは、考えてみれば不思議なことだ。本能という言葉だけではくくれない複雑さがそこにある。
私も子供を産んだとき、授乳に苦しむ母たちの姿を見た。子供がミルクを飲んでくれないと泣きながら苦しむ母を見ながら、食物を得ることは大変なことなのだなあと思ったことを思い出した。
私達はつながりのなかで、食べることなど、ハビトゥスを学んでゆく。摂食障害はそのつながりを手放してゆくことなのではないか。そして、ふつうに食べられないことで、さらに孤立化していく。人間は心底関係性の生き物なのだと感じた。
家族モデルが、救済をもたらす一方、その関係性のなかに閉じ込められてしまう指摘も面白いなと思った 。自分も両親との関係で難しさを感じている。信田さよこさんの本で書かれていたように、自責から逃れるために、家族モデルを知ることはひとつの救いになる。だけど、そのさきに、母との関係性であるという主人公を降りることが必要なのだなとも思っていた。
文化人類学のイメージも拡がった。文化人類学は、海外でフィールドワークをするというステレオタイプがあったけど、それだけではないのだなと思った。これは社会学におけるヒアリングやインタビューとは何が違うのか?とも思った。(この辺りは継続で学ぶ、考えることをしてもいいかもしれない。)
人と出会い、そのことによって、いま生きているこの自らの社会を相対化することという意味において、まさに文化人類学なんだなと思う。
著者の人と関わるうえでの姿勢というか愛も感じた。患者として一般化するのではなく、いまを生きるひとりの人として出会うこと、それによって医療として数字や症状としてとらえることとは違うことが見えてくる。 -
はじめに
本書はあやかさんの読書ログをきっかけに読みました。ご紹介ありがとうございました!
https://bc-liber.com/blogs/2b29b2cc1269
なぜ普通に食べられないのか
あやか
09/11 16:20
私は医師であり、現在摂食障害の方を一人、継続的に診療しています。そういう意味で非常に関心の高い話題だったため、まとめてみることにしました。
*精神科医ではなく、家庭医療専門医という専門医資格を持っています。ざっくり言うと、「町医者を専門的にやってる」医者です。
概要
本書は、摂食障害という精神疾患を持つ6名の女性へのインタビューを通して、摂食障害の内実や、ひいては人が食べて生きることの意味を多面的に考察した本です。
個々の女性の具体的エピソードは省略しますが、読んでいてなかなか辛いものがあります。
この読書ログでは、本書の主張を4点にまとめてみました。
・やせることの社会的意味とジェンダー差
・依存性(フローと非日常体験)
・家族関係の問題のせいで摂食障害になったのか?
・食体験の視点の複層化
やせることの社会的意味とジェンダー差
日本や西欧社会では、一般にやせていることが美しさの基本条件とされています。
「デブ専」のように太った人を好む方もいますが、これはあくまでやせているのが美しいというのが一般認識であるからこそ生まれた言葉ですよね。
なぜこうした認識が生まれたのか?本書では3つの社会的な要素を指摘しています。
1つは、食料事情です。大昔、狩猟社会から農耕社会に移行することにより、貧富の差が生まれました。その頃は太ることは富の象徴であり、上流階級の証でした。更に時代が進むと工業化が進み、貧しい人でも簡単に太ることができる社会になりました。そのことにより、太ることは社会的なステータスではなくなります。
2つ目は、医療の変化です。以前は病気を防ぐことよりも、病気を発症した人の救命が医療の中心でした。医療進歩などにより救命がある程度可能になってくると、病気を早期発見したり発症を予防したりという予防医学的な発想が進んできます。
様々なライフスタイルが病気のリスクになることがわかると、ライフスタイルに介入するという発想が生まれ、更にライフスタイルを管理するのは自己責任だという価値観が生まれます。
3点目は、個性の追求です。外的な価値観として宗教・国家・科学・資本主義などがありますが、現代に生きる我々の多くはそれらを絶対的な価値観として信じ切ることができません(本書では、「大きな物語を失った」時代と表現しています)。その代わりに、私たちは自分自身に価値観を置き、それを重視することが求められます。個性とか自分らしさと呼ばれる類のものですね。
個性を表現する中で、身体もその対象となります。メンテナンスを行い、引き締まった身体により他者との差異化を図り、自分自身を表現することとが重要視されることになります。
また、やせることの社会的意味にはジェンダー差があります。
結婚相手に求める条件を男女に聞いた調査によると、男女とも共通したのは人柄や家事の能力、仕事への理解などでした。一方で、男女差があったのは、女性は男性の経済力や職業などの社会的地位を重視する傾向があったのに対して、男性は女性の容姿を重視する傾向があったことです。
また、社会の現実と学校教育の矛盾も重要な問題です。女性は、学校教育では(表向き)学力などが評価されるが、現実社会では容姿が重要視される。実際、日本では20代や30代の女性のやせすぎが多いことが指摘されており、この矛盾の証左とも考えられます。
依存性(フローと非日常体験)
なぜ摂食障害の方(の多く)は過食をやめられないのか?過食には一種の依存性があるからだと本書では語られます。依存になるのは、以下のような条件が満たされるからです。
①適度に難しい(より多く食べられて吐き出せる食材の選定や食べる順番の工夫)
②明確なルールがある(できるだけ多く食べ、吐き出す)
③自己没頭できる=フロー状態になれる
④強力なフロー状態になれるため、他の代替行動では満足できない
*前述のあやかさんの読書ログから引用(一部太字をやめ、下線に変更)
また、過食の対象となる食べ物はキャベツなどではなく、かつ丼や菓子パンなどの不健康的な食べ物ですが、これにも理由があります。過食はある意味で非日常体験なのです。
誕生日にケーキを食べるように、正月に餅を食べるように、祝祭の時には特別な食事がふるまわれます。普段は食べない不健康な食べ物をあえて食べることにより過食は非日常体験となり、日常の辛さを一時的に忘れることができるのです。
ただし、通常の祝祭と異なり、過食は悲しい祝祭です。この非日常体験は記憶に残したいものではなく、誰かと共有したいものでもないからです。
家族関係の問題のせいで摂食障害になったのか?
摂食障害において、医学的に原因と推定されているものは幾つかありますが、特に重要視されているものの一つは家族(母子)関係です。特に母親の過保護や過干渉、家族内の不和などが一般に言われています。
確かに本書で出てくるどのエピソードでも家族関係に問題があることが伺えますが、家族関係が改善すれば必ずしも摂食障害が改善するとは限りません。
また、他国の例も挙げられており、シンガポールでは家族関係を摂食障害の原因とする論調は少ないそうです。むしろ欧米化の影響や、肥満対策の政策の影響が指摘されています。シンガポールでは働く女性が多く、子供の問題を母に落とし込む見方になりがちな日本とは考え方が異なるのかもしれません。
食体験の視点の複層化
私たちが食事をするとき、無意識のうちに色んな背景知識を用いています。
・食べていいものはどれか?(韓国では犬食がありますが、日本だと食べないですよね)
・食材の入手法は?加工や保存方法は?
・どうやって食べるのか?(レストランで、床に座って食べたりはしないですね)
家族や学校の給食など、様々な他者との関わりの中で、私たちはこうした知識を徐々に身に着けていきます(=ハビトゥス)。背景知識には必ずしも合理的理由があるわけではありませんが、食習慣を通じて他者と連帯することができます。「同じ釜の飯を食う」というやつですね。こうした食事は、感覚的・体験的なものです。
一方で、カロリーや体重といった科学的な視点から食事を見ることもできます。これは食べ物を数値で捉えなおした食事のあり方であり、そうした意味で概念的です。
現代を生きる私たちは、感覚的・体験的な食事の仕方と、概念的な食事の仕方と、両方の視点を持っているように思います。
摂食障害の人は感覚的・体験的な食事ができなくなっており、食事を概念的にしか捉えられなくなっている、という言い方もできるかもしれません。感覚的・体験的な食事ができないと、食事を通じた他者との連帯が難しくなり、人間関係の構築や維持が難しくなるのかもしれません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以下、感想です。
まず、過食の依存性というのは言われてみれば尤もですが、あまり考えたことのない視点でした。医学書でもあまり指摘されているのを見たことがなく、摂食障害の難しさの一端を垣間見た気がしました。
また、家族関係が摂食障害に関連するというのもよく見かける論調の一つですが、本書はどちらかというとそれに否定的で、そのことも新鮮でした。
全体を通して、疾患を医学以外の視座から眺めてみるというのは、非常に興味深かったです。本書を実臨床でそのまま活かせるかは分かりませんが、患者さんと向き合う上で参考になる一冊でした。 -
自分がまあまあ普通に食べられない勢なのでなにかヒントでも…と思い読んでみたけどこの本でインタビューに答えてる人達はわたしの一億倍くらい壮絶で苦しんだ過去があって、すみません…と思ってしまった。摂食障害の四文字でも様相は色とりどりであることだった。
「還元主義」の構造はなるほどそうだなと思う。
摂食障害はどのルートを辿ってもある結論やモデルに落とし込まれてしまうループものというか、けどそれにより自分の中にモデルを発見することで摂食障害から脱却する足掛かりを得る人もいる。
摂食障害を理解するアプローチは当事者にとっても複雑なのだ。
けどある人のインタビューで「夕飯の菓子パンを楽しむために朝昼抜く」っていう、いわば夜の菓子パンが「祝祭」になってるという話、めっちゃわかる…と思った。
私も学生時代に夜のマクドを心置きなく楽しみたいから平気で朝昼抜いてた(そして痩せた)あれは祝祭だったのか…なんてしっくりくる言葉… -
筆者が本書の中で「専門家から見て正しい心身をつくるために生きているのか」との問いかけにハッとしてしまいました。
食というのはまず自分のため、生きるためにあるのだということを覚えておきたいと心に深く刻む一冊でした。 -
【本学OPACへのリンク☟】
https://opac123.tsuda.ac.jp/opac/volume/704089 -
「人生の過程においてふつうに食べられなくなった6人の女性にインタビューし、「拒食や過食がやめられない」という一見大多数の人とはかけ離れた女性の人生の中に、人が食べて生きることの根源的な意味を見出す。」
〈磯野真穂〉
早稲田大学文学研究科博士後期課程修了。国際医療福祉大学大学院講師(博士(文学))。医療人類学専攻。現役の医療者に向け文化人類学を教える傍ら、医療現場でのフィールドワークを続ける。
著者プロフィール
磯野真穂の作品











 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :