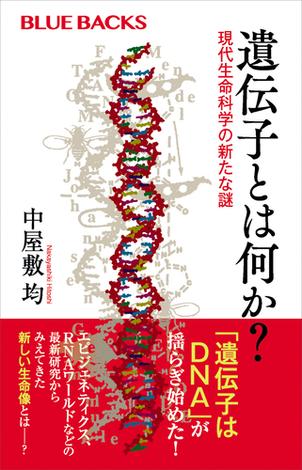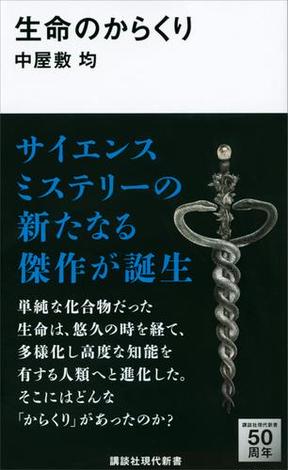- Amazon.co.jp ・本 (208ページ)
- / ISBN・EAN: 9784062882682
作品紹介・あらすじ
現在の地球に存在する多様な生き物たちは、単純な化合物から進化してきたと考えられている。「生命」が単なる物質から決別し、その脈打つ「鼓動」を得たのは、どんな出来事が転換点となったのだろうか? 本書では、最近の生命科学の進展から得られた数々の知見を通じて、生命の根源的な性質を「自己情報の保存とその変革」という二つの要素と捉える。これらが悠久の時を経て織りなす「生命」という現象の「からくり」に迫る。
感想・レビュー・書評
-
私は生粋の文系人間で、理数系の書籍はことごとく避けてきたが、生命の起源とか原理に興味が湧いたので覚悟を決めて本書を手に取ってみた。
本書の趣旨はシンプルで、生命の設計図に当たるDNAは自己情報の保存と変革の相反する性質を内包しており、それゆえ弁証法的に生物が今日の姿まで発展してきたというものである。後半では人間の文明の発展も同様で、過去の偉人の知見を元に各時代の天才達が新しい1ページを書き足して来た歴史に触れている。
生命の起源については軽く触れられているのみだが、最新の有力な説としては、海底の熱水噴出孔から始まったのでは無いかということだ。なお、核戦争が起きて地上の生物が全滅しても、まだ海底には古細菌が脈々と生きているのでいずれ再生するだろうという、謎にポジティブな主張が面白かった笑
科学的な事例のみではなく、哲学や歴史など文系的な事象と絡めながら説明されているので、文系人間にも分かりやすいだけではなく、科学のロマンみたいなものまで感じられた。読みごたえのある文章展開がしっくりきたので、別の著書も読みたくなった。
詳細をみるコメント0件をすべて表示 -
順序が逆だが、最近の著書『ウイルスは生きている』が心に残ったので、著者が一般人を対象にした最初の著作である本書を読んだ。
『ウイルスは・・』では、ウイルスと細菌の差は、一般的に理解されているより曖昧なのだと感じたが、本書では生物と非生物も、線を引きたくても定義自体が曖昧で、同じくグラデーションのようなものだと感じた。
本書も巧みな例えや文章の上手さが光る。読んだばかりだが次作が待ち遠しい。 -
『ウイルスは生きている』からの流れでもう1冊読んでみました。科学史や最新学説の解説ではなくしばしばやや哲学的に「生命とは何なのか」「生命に特徴的なこととは何か」を考えることが本書のテーマです。
読んでいて印象に残ったのは2点。まず1点目は「化学進化説」を前提とし、無機物と有機物、ウイルスと細胞を持つ生物、「独立」して生きる生物とそうでないものとの間に、本質的な線引きなど不可能であること、また「進化」というのが能動的な過程などではなく「淘汰」と「偶然」の積み重ねによる結果論でしかないことを強調する筆者にとっても、生命の「進化」の過程の記述は目的論的なものとならざるをえないことです。「生命」を論じるときに独特のこのバイアス──「生命」について論じるコンテキストでありさえすれば仮にそれがDNAやRNAといった分子のスケールの実体であっても「戦術」や「戦略」を練る主体となりうるというこのバイアス──は、どうも私たちの思考、私たちの意識というもののある限界を示しているような気がしてきます。
もう2点目は第5章で展開されている「生物」と「非生物」の再定義の試みです。このなかで筆者は生物の特徴をその双方向の作用力(相補性)にあるとしています。非生物(例えば鉱物)も結晶化や触媒作用などで他の物質に影響を与えその構造を変化させたりすることはできる。けれども生物(その最小単位は著者の考えではヌクレオチド)ではその作用が双方向である、と。
すなわちヌクレオチド(DNA・RNAなど)はその化学的構造ゆえに自身の複製を生じさせ、そこからアミノ酸を、さらに自身の複製過程に影響するタンパク質をも生ぜしめる。タンパク質はその他の分子とともに細胞の構造材ともなる。細胞生物は互いに飲み込み飲み込まれて、あるいはオルガネラになりはて、あるいは寄生生物に踏みとどまり、何にせよより構造化された状態をとるようになる。細胞と細胞は互いにくっつき合い、分化しあって多細胞生物を生み出す。さらにそれら生物同士は生態系を構成して互いの「淘汰」や「偶然」に作用し合う。そして人間に顕著なように、生物は自身の外側に、個体と個体のその「あいだ」にあるる生物・非生物に作用して何がしかのもの──単なる道具のような具象的なものから文化や制度そして科学(!)のような抽象的なものまで──を生じさせ、それがまた自身のあり方に影響を与える・・・。
ようするに「構造化する構造」、構造化する主体であると同時の客体でもある構造、自己の状態をもとに自己をも含む外部の状態に影響を及ぼし、そこからまた影響を受けるという、再帰的・反射的なはたらきをするオートマトンのイメージです。このイメージの中ではもはやどこまでが「独立」した個体だとか、どこまでが「生物」だとか、そういった議論は意味をなさない。ただ全体としての構造化の運動があるだけです。
まあちょっと概念遊び的な感じもしますが、ヌクレオチドという生化学的な実体からはじめて社会・文化という人文科学的な実体にまでつながるのはちょっと気持ちいいものです。 -
摂南大学図書館OPACへ⇒
https://opac2.lib.setsunan.ac.jp/webopac/BB99671982 -
忠生図書館2017.9.7 期限9/21 読了9/7 返却9/8
-
それなりに高度な内容だが文章が読みやすい。DNAやウィルスといった、なんとなくわかったつもりになっているけど、じつはよくわかっていないものを説明してくれる名著。
-
一定の専門性を確保しつつ、明確なモチーフ(有用情報の漸進的蓄積。保存と変化)を下敷きに、一書がものされている。とりわけ最後のDNAから文明論にいたる考察は深い。
生命の起源に関する記述はよくあるもので、かつ少なめ。
・単純な競争で考えると無性生殖のほうが有利である場合が圧倒的に多い。
・有性生殖による全ゲノムのシャッフリングは、組み合わせによる多様性の創出であり、それ自体には遺伝子の突然変異を必要としないため、例外的なものを除けば、致死性は生じない。
・より広く考えれば、「生命」という現象にとっては、個体とは何か、個体の独立とは何か、あるいは種とは何か、もっと言えば種が絶滅したのか存続しているのかといったことさえ、おそらく「どうでも良いこと」であり、「その現象の継続」、すなわち「情報の保存」と「情報の変革」を繰り返し、新たな有用情報を蓄積していく現象、それがいかなる環境下においても継続していくことが唯一大切なのではないだろうか。
・生命とは核酸という物質的装置により、「幸運を蓄積する」情報のサイクルを展開することが可能になった存在と言えるのではないだろうか。
・この世の形あるものたちが、必ずしも何らかの「設計図」により作られているのではなく、分子の形、そのものが設計図であり、一定の環境さえ与えられれば、特定の形に自然に組み上がるようなことが起こり得ることを示している。
・カール・セーガン:人間の持つ情報。1.DNAによる「遺伝情報」。2.脳細胞のネットワークからなる「脳情報」
・化学進化の中での核酸の出現:文字を基盤とした「外部メモリー」の発達 -
「生命」の持つ根源的なシステムについて、分子生物学の最先端の知見を踏まえて考察している。
著者はまず、生命と非生命の境界について、細胞内小器官(葉緑体、ミトコンドリア等)、細胞内共生細菌、巨大ウイルス等を例に、細胞膜の有無、他の生物への依存関係の有無、ゲノムサイズ・遺伝子数等の観点から考察し、「そこになんらかの明確な区切りを引くことはきわめて困難である」が、これらの例の「「生き様」は、所謂、ある「一つの現象」が多様な環境に適応して姿を変えているだけに過ぎない」と述べる。
そして、「一つの現象」の本質とは、「自分と同じものを作ること(=情報の保存)」と「自分と違うものを作ること(=情報の変革)」という相矛盾した二つであり、生物は、どちらか一方に偏ってしまっては「生命」が成り立たない、その究極の矛盾のバランスを保つために、以下のようなシステムを生み出し、保ち続けているのだという。
◆2本あるDNAの複製プロセスは異なった方式を採用しており、一方は変異が起こりにくい方式で、もう一方は変異が起こりやすい方式である。(不均衡進化)
◆高等生物は、理屈上は1セットで足りるゲノムを、2セット持っている。
◆無性生殖より様々なコストがかかるにも係らず、高等生物は有性生殖行っている。
そして、こうしたシステムによって「情報の保存」と「情報の変革」が、途方もない時間、延々と繰り返され、無数の偶然から幸運を選んではその情報が蓄積されて、現在の生物が存在しており、それこそが「ダーウィン進化」と呼ばれるものであり、「生命のからくり」なのだという。
著者は「生命」について、「「生命」という現象にとっては、個体とは何か、個体の独立とは何か、あるいは種とは何か、もっと言えば種が絶滅したのか存続しているのかといったことさえ、おそらく、「どうでも良いこと」であり、「その現象の継続」・・・いかなる環境下においても継続していくことが唯一大切なのではないだろうか。個体や種というものは、その継続を強固にするために「生命」が環境に応じて編み出したバリエーションに過ぎない。それらを通じて継続する現象こそが、「生命」の本質であり、その過程で生じた個々の形態、生態によって「生命」を定義しようとする試みは、実は形にとらわれ、実態から離れた霞か雲を掴むような話なのかもしれない。」とも語っている。
「生」とは何か、生命科学の視点からヒントを与えてくれる。
(2015年1月了) -
ありきたりな表現で恐縮ですが、非常に興味深いものでした。生命は美しい、今、起きている様々な苦難も、驚くべきことも、ノイズのように見えることも、すべては生命の大きなリズムと流れの中にある。そういうことを思い浮かべました。
核酸に内包された情報の保存と情報の変革のサイクルが機能し始めた時、「情報の蓄積システム」が地球上に現れ、それが「生命という現象」であり、最初の情報革命であった、そして、地球上の生物のうち、人類が文字情報を獲得し、保存と変革のサイクルを手中にしたとき、第2の情報革命が起きたとする本書は、人類の文明の歴史の中に、生命、DNAが刻むリズムに由来する何かを見てとります。本書が解き明かしていくDNAの二重らせん、陰と陽のリズム、「逸脱」「非調和」の織りなす生命のありようは、この宇宙の本質に想いを馳せさせてくれます。いい本でした。
著者プロフィール
中屋敷均の作品










 本棚登録 :
本棚登録 :  感想 :
感想 :