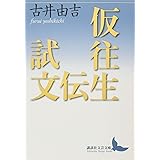年老いた人間の内面と周囲世界が朦朧と混じり合っているというか、どれが今でどれが記憶なのか、どれが幻想でどれが真実なのかも判然としないが、とにかく小説自体は前に進んでゆく。だが文章がこの世界をふらふらとうろついているようでもあり、前に進んでいるのか後ろに戻っているのかもわからないような感覚を抱く。だが作中人物はちゃんと世の中に付いていくことはできているようであり、老いているとは言え、世界と自分の存在に対する分別のようなものはあるのである。だから文章は各々難解過ぎもせず単純過ぎもせず、結構気持ちよく読める。
言葉の選ばれ方、構文などが枯淡でかつ重みがあり、その文章センスがそのまま老境を生きる心理的な処世ともなっているようだ。そこに、この小説が心地よく読める秘密があるような気がする。

無料のKindleアプリをダウンロードして、スマートフォン、タブレット、またはコンピューターで今すぐKindle本を読むことができます。Kindleデバイスは必要ありません。
ウェブ版Kindleなら、お使いのブラウザですぐにお読みいただけます。
携帯電話のカメラを使用する - 以下のコードをスキャンし、Kindleアプリをダウンロードしてください。

野川 単行本 – 2004/5/29
古井 由吉
(著)
現代日本文学の最高峰を示す傑作長篇小説。誰でもそれぞれの死後を今に生きている。戦後半世紀余の時間を往還し死者と生者の混交する世界と日常の中の永却を描く芥川賞・谷崎賞・読売賞受賞作家の到達点。
- 本の長さ314ページ
- 言語日本語
- 出版社講談社
- 発売日2004/5/29
- ISBN-10406212341X
- ISBN-13978-4062123419
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
商品の説明
内容(「MARC」データベースより)
すべて過ぎ去り、しかも留まる-。戦後半世紀余の時空を往還し喧噪の彼方へ耳を澄ませば、幽明の境に死者たちはさざめき生者は永遠の相へ静まる。長篇小説。『群像』連載を単行本化。
登録情報
- 出版社 : 講談社 (2004/5/29)
- 発売日 : 2004/5/29
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 314ページ
- ISBN-10 : 406212341X
- ISBN-13 : 978-4062123419
- Amazon 売れ筋ランキング: - 670,118位本 (本の売れ筋ランキングを見る)
- - 15,301位日本文学
- カスタマーレビュー:
著者について
著者をフォローして、新作のアップデートや改善されたおすすめを入手してください。

1937年、東京生まれ。東京大学大学院独文科卒。71年「杳子」で第64回芥川賞を受賞。80年『栖』で日本文学大賞、83年『槿』で谷崎潤一郎賞、87年「中山坂」で川端康成文学賞、90年『仮往生伝試文』で読売文学賞、97年『白髪の唄』で毎日芸術賞を受賞(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『 やすらい花 (ISBN-13:978-4103192091)』が刊行された当時に掲載されていたものです)
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2006年4月26日に日本でレビュー済み
読みながら何度かまどろみ、はっとして先を読んだ……というのが古井作品の場合は褒め言葉だ。なぜなら作品の語り手も、たいていは寝入りばなのまどろみにあるようだから。
繰り返し語られるのは、友人が大空襲に遇った幼い日、半ば眠りながら母に手を引かれて歩いた時の情景と、別の友人が、青年の頃、下宿の年上の女主人と奇妙な関係を結んだ夜々の情景なのだが、空襲の日に病の父が焼死したのではないか、という語り手の疑問は解かれず、下宿の女主人も、生きているのか死んでいるのか判然としない謎の女だ。そのうちに友人からの聞き語りと語り手自身の回想も入り混じるように思われ、しまいには、この作品と過去に読んだ古井作品も、自分の中で入り混じる。
そもそも生きるとは夢と現の間を揺れることなのかも知れず、亡くなった友人井斐はまだ生きているように思われ、逆に毎年同じような年賀状のやり取りをしている友人内山はもうこの世にいないように思える。こういう世界観を、言葉の力だけで起ち上げるのが、古井作品の凄さだ。その凄さに、何度も改めて魅了される。
まどろみつつ時間をかけて読み、最終章「一滴の水」にたどりついてふいにはっきりと目が覚め、食い入るように読んだ。十八歳の頃、語り手と井斐が、土曜の放課後の屋上で遭遇した銀杏の大木の黄葉の禍々しいまでに鮮やかな光景、そして語り手の行き着く境地……あるいは人は死後を生きているのかも知れず、肉体の死は、こんなふうに唐突に訪れるのかも知れない。
繰り返し語られるのは、友人が大空襲に遇った幼い日、半ば眠りながら母に手を引かれて歩いた時の情景と、別の友人が、青年の頃、下宿の年上の女主人と奇妙な関係を結んだ夜々の情景なのだが、空襲の日に病の父が焼死したのではないか、という語り手の疑問は解かれず、下宿の女主人も、生きているのか死んでいるのか判然としない謎の女だ。そのうちに友人からの聞き語りと語り手自身の回想も入り混じるように思われ、しまいには、この作品と過去に読んだ古井作品も、自分の中で入り混じる。
そもそも生きるとは夢と現の間を揺れることなのかも知れず、亡くなった友人井斐はまだ生きているように思われ、逆に毎年同じような年賀状のやり取りをしている友人内山はもうこの世にいないように思える。こういう世界観を、言葉の力だけで起ち上げるのが、古井作品の凄さだ。その凄さに、何度も改めて魅了される。
まどろみつつ時間をかけて読み、最終章「一滴の水」にたどりついてふいにはっきりと目が覚め、食い入るように読んだ。十八歳の頃、語り手と井斐が、土曜の放課後の屋上で遭遇した銀杏の大木の黄葉の禍々しいまでに鮮やかな光景、そして語り手の行き着く境地……あるいは人は死後を生きているのかも知れず、肉体の死は、こんなふうに唐突に訪れるのかも知れない。
2021年3月15日に日本でレビュー済み
○ これを小説と言ってよいものだろうか。よく眼にする小説とは全然趣が違う。
○ まるで独白のような身辺雑記のようなものであるが、作者は事実をそのまま書いたのではなさそうだ。潤色と創作があるから分類すれば小説と言うしかないということなのだろうか。
○ ストーリーはないようなもので、時間の前後もはっきりしない。それどころか現実の話か夢の話かもなかなか判然としない。
○ 「足取り」とか、「背中」とか、「土手」とかいうキーワードを起点としてあちらこちらに話が飛躍する。どのエピソードでも、記述は常に主人公(文中で男と言ったり、私と言ったりする)の心に残った印象が中心である。情景や風景の描写すら主人公の心の中に映るものを掬い取ったようなもので、これを心の中を覗く描写とか求心的な記述とか言うのかもしれないが、正直に言えば少々独りよがりな気もする。誰があんたの細々とした心の動きに興味があるものかとそっぽを向きたくもなるのだ。
○ しかしながら、それでは全然魅力がないかと問われれば、そう言い切るのは惜しい気もしてくる。そうしたものの叙述に注ぎ込まれた文章の技を見どころとする作品であるように思う。だから、この作品は早くは読めない。筋を追ってどんどん読み進むようなものではなく、作者の独白にじっくりと付き合うしかない。
○ まるで独白のような身辺雑記のようなものであるが、作者は事実をそのまま書いたのではなさそうだ。潤色と創作があるから分類すれば小説と言うしかないということなのだろうか。
○ ストーリーはないようなもので、時間の前後もはっきりしない。それどころか現実の話か夢の話かもなかなか判然としない。
○ 「足取り」とか、「背中」とか、「土手」とかいうキーワードを起点としてあちらこちらに話が飛躍する。どのエピソードでも、記述は常に主人公(文中で男と言ったり、私と言ったりする)の心に残った印象が中心である。情景や風景の描写すら主人公の心の中に映るものを掬い取ったようなもので、これを心の中を覗く描写とか求心的な記述とか言うのかもしれないが、正直に言えば少々独りよがりな気もする。誰があんたの細々とした心の動きに興味があるものかとそっぽを向きたくもなるのだ。
○ しかしながら、それでは全然魅力がないかと問われれば、そう言い切るのは惜しい気もしてくる。そうしたものの叙述に注ぎ込まれた文章の技を見どころとする作品であるように思う。だから、この作品は早くは読めない。筋を追ってどんどん読み進むようなものではなく、作者の独白にじっくりと付き合うしかない。
2006年4月20日に日本でレビュー済み
読み終えたとき、これはある種の遺書なのではないか、と思った。古井氏の、古井文学の、そして文学それ自体の遺書なのではないか、と。
大袈裟な言い方かもしれない。
しかし、この作品のなかで起こっている事態はただ事ではない。なによりも、言葉の存在論的な無重力化ともいうべき出来事が、従来の古井節を廃棄する形で、ひそかに生起してしまっているということ。この実に特異で奇跡的な〈軽さ〉をおのれの書法において実現してしまった後で、なおも文を書き継ぐことが果たして可能なのか? この作品を「ある種の遺書」と呼んだのは、まさにこの意味においてである。
にもかかわらず、この作品を書き終えた古井氏は、まるでなにごとも起こらなかったかのような涼しい顔で、すぐさま新たな連載(『辻』)に取りかかる。
いやはや、おそるべし、と言うほかない。
大袈裟な言い方かもしれない。
しかし、この作品のなかで起こっている事態はただ事ではない。なによりも、言葉の存在論的な無重力化ともいうべき出来事が、従来の古井節を廃棄する形で、ひそかに生起してしまっているということ。この実に特異で奇跡的な〈軽さ〉をおのれの書法において実現してしまった後で、なおも文を書き継ぐことが果たして可能なのか? この作品を「ある種の遺書」と呼んだのは、まさにこの意味においてである。
にもかかわらず、この作品を書き終えた古井氏は、まるでなにごとも起こらなかったかのような涼しい顔で、すぐさま新たな連載(『辻』)に取りかかる。
いやはや、おそるべし、と言うほかない。
2005年5月1日に日本でレビュー済み
この作品での語り口は、かつての饒舌さが失せ、古井の心の奥底から言葉が、立ち現れるかのような趣がある。その中から、人の優しさがそこはかとなく香り立つ。とにかく美しい作品だ。